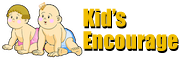卒園おめでとう!
3月18日土曜日に、令和4年度の卒園証書授与式が行われました。
あいにく雨になった天気でしたが、園内は子どもたちが自分たちの卒園式のために準備をした、たくさんの装飾で彩られ華やかな雰囲気に包まれました。
家族の方々や職員が見守る中、少しの緊張感と、誇らしげな表情をした卒園児が堂々と入場してきて卒園式が始まります。


初めに卒園証書授与です。一人ずつ名前を呼ばれ、前に出て証書を受け取り、自分の名前、入学する学校名、園生活で楽しかったこと、小学校で頑張りたいことをそれぞれに話しました。緊張してちょっと話すことを忘れてしまい、後ろにいる園長にそっと耳打ちしてもらう子もいましたが、しっかり前を見て話す姿は、とても立派でした。
ちなみに、楽しかったことの一番人気は、リハーサルまでは遠足でした。当日、子どもたちは自分の楽しかったことを改めて考えてきて、遠足、クッキーづくり、水遊び、宝探し等、様々に印象に残った活動を発表していました。学校に行って頑張りたいことは、算数のほか、漢字、体育という子もいました。




次に、園長の挨拶と保護者の代表の方のお話がありました。子どもたちは少しそわそわしながらも静かに真剣に話を聞いていました。
そしてその後は毎年恒例となっている卒園児の発表です。幼児になってから日々の活動や課業で身につけてきた成果を、「大きくなったよ!」という姿を家族に見てもらうことが、例年子どもたちの卒園式にかける大きな意欲になっています。
今年は、ダンスと合奏をしました。ダンスは、表現発表会と同じ、「TONIGHT 」を新たにフォーメーションをつけてブラッシュアップして踊りました。フォーメーションが少し複雑でなかなかカウントが取れずに、前日まで繰り返し確認していた子どもたちでしたが、本番はバッチリ1回で決まりました。




合奏曲は、「愛は勝つ」を鍵盤ハーモニカ、グロッケン、カホン、ボンゴ、鈴、タンバリンとそれぞれにパートを持っての演奏です。自分のパートだけではなく、それぞれのパートの音を聞き合い、テンポを合わせることを意識しながら演奏することは大人でも難しいのですが、自分が奏でている音とは違う音程やリズムを聞きながら、自分がそれに合わせて演奏するという課題も、しっかりと聞き合いながら演奏し、最後は歌で締めくくるという幅の広い合奏に挑戦しました。歌声も柔らかできれいな聞きやすい声が、保護者の方々の感動を誘っていたようでした。




子どもたちの発表の後は、活動の軌跡をスライドショーで保育園での生活の思い出を皆で振り返りました。
自分たちがしてきた活動を、「この時、○○したよね」「あ、○○ちゃんがいる」などと子ども同士でもおうちの方とも振り返りながら楽しそうに見ていました。
最後は園歌「どんどんどん」を歌いました。音楽課業でも様々な行事でもたくさん歌ってきたどんどんどん。この皆で歌うのはこれが最後。身振りも大きく、張り切って歌っていました。


精一杯、今の自分たちの力を表現し、最後に卒園児退場の時を迎えました。おうちの方の拍手に送られながら、職員が作ったアーチをくぐっていく子どもたち。どの子も自分たちの卒園式をしっかりとやり遂げた充実感のある表情をしていました。
今日の誇らしい経験を経て、またひとつ大きくなりましたね。保育園でのたくさんの経験を糧に、学校生活も生き生きと充実したものにしていって欲しいと願っています。
卒園おめでとう!