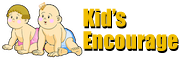9月16日(金)にミニお話会を行いました。
今回はコロナの自粛期間の関係もあり、子どもたちが密にならないように配慮した上で、年長のクローバー組の子どもたちが発表をする側となり、年少と年中の子どもたちがお話会を見る側となって、“ミニお話会”と行うということになりました。
お話会の2週間前、年長の子どもたちに「9月のお話会はクローバーさんがお話をしてみない?」と提案してみると、「いいね!」「やりたい!」「できるかな!?」とたくさんの声があがりました。
以前、7月の七夕会のときに一度お話の発表をしたことがあるという経験から、今回は子どもたちもイメージを持ちやすかったようで、子どもたち同士で「なんの役がやりたい?」「わたしは○○かな!」などと会話が広がっていき、すぐに活動に取り組もうとする意欲が見られました。
さて今回のお話は、ペープサートによる『うちのこまるをしりませんか?』です。
お月見の日。団子屋さんのだんごむしの一家の子どものひとり“こまる”が迷子になってしまいました。だんごむしの一家はこまる探しへ出かけます。
果たしてこまるは見つかったのか・・・?
年長の子どもたちは、絵本の読み聞かせを聞いているときから「ちちまるの役がいい!」「こまるがやりたい!」「○○ちゃんは○○の役がいいかな?」「○○の役もいいな!」と、自分たちがお話の発表をするにあたって、自分がやりたい役や友だちにぴったりの役は?など、子どもたち同士で意見を交わしながら期待を高めていく姿がありました。
子どもたちが相談しながら役を決めると、いよいよ練習が始まりました。
ペープサートのイラストを見て「こんなふうに言ってみたらいいかも!」「このときはどんな気持ちかな?」「みんなで声を合わせて言ったほうが聞こえるよ!」などと、絵本で読んだストーリーを思い浮かべながら、自分たちの言葉に変換して表現をしたり、声の大きさやペープサートの動かし方についても意見を出し合ったりしながら、試行錯誤する子どもたちでした。
年中や年少の子どもたちへのサプライズにするために、お話会のことはみんなに内緒にしながら、毎日少しずつ練習を重ねていきました。
お話会前日になり「明日が本番だね!」「最後の練習だ!」と張りきっているときに、担任の平野が子どもたちに「お話会のはじまりとおわりはどうしようか?どうやってお話をはじめるようにしたい?」と問いかけてみました。
すると「はじめは“これからはじまります!みてください!”って言う!」「おわりは“見てくれてありがとうございました”でいいかな?」
と、お話会にきてくれるお客さんのことを考えて、どうしたらお話会を楽しんでもらえるか?ということを子どもたち自身が考えながら、会を成功させるために意見を出し合い、より良いものにしようという子どもたちの熱い気持ちが感じられました。
そして迎えたお話会当日。
「ちょっと緊張する!」「上手にできるかな?」とちょっぴりドキドキの気持ちを感じながらも「みんなでがんばろう!」と期待が高まる子どもたち。
みんなで円陣を組み「がんばるぞ!エイエイオー!」と気合を入れてスタンバイしました。
お話が始まると、子どもたち同士が舞台の裏で一生懸命に台詞を言ったり、自分の出番を真剣な表情で待ちながら構えていたり、台詞を忘れてしまった子にこっそり教えてあげたりと、子どもたちそれぞれが自分の力を精一杯出しながら、みんなで協力してお話を発表する姿がありました。
お話が終わり、クローバーの子どもたち全員が舞台の前へ出て「見てくれてありがとうございました!」とあいさつをすると、お客さんから拍手をもらい、嬉しそうな子どもたちでした。
お話会が終わるとすぐに「楽しかった!」「ちょっとまちがえちゃった!」「またやりたい!」とすでに次回へ向けての期待をもつ様子も見られ、“もっとやりたい!”“もっと上手になりたい!”という向上心の高さに、子どもたちの無限の可能性を感じました。
今回、子どもたちは『友達と協力して目的を成し遂げることができた』という経験をすることができました。
年長の子どもたちにとって、残り約半年の保育園生活です。
今後の活動でも、子どもたちが友だちとの仲間関係を深めながら、自分の好きなことやしたいこと、興味のあることに全力で取り組んでいってほしいと思います。