年末年始、お天気に恵まれて皆さま穏やかに過ごされているでしょうか。
年末には、久しぶりの旅行や里帰りを予定しているというお話が子どもたちから出ていたので、ご家族での時間を元気に楽しんでいるといいなと思います。
ただ、コロナ流行はまだ油断できない状況なので、皆さまどうぞ自衛なさりながらお過ごしください。



長引くコロナ感染の影響ですが、できる感染対策をしながら、子どもたちの活動が制約されたものばかりにならないように工夫しながら、保育園でも様々な活動に取り組んできました。
特に幼児は自分たちで考え、行為していけるような内容を重視しながら日々の保育を積み重ね、10月の宝探し会や12月の表現発表会に取り組み、新しいことにチャレンジしながら友達と協力することや、助け合うことなどを子どもたちは能動的に経験できたように思います。
そうした活動を通じて、子ども同士の仲間関係に広がりができ、いろいろなお友達と一緒に遊ぶことが自然にできるようになっていきました。
こうした子どもの姿から、日常の活動が豊かになり、そこで子ども自身が主体的に自分たちの遊びを行っていけるような環境づくりと保育者自身が環境であることの自覚がますます大切になっていると、昨今の社会的な「保育の問題」から感じることです。

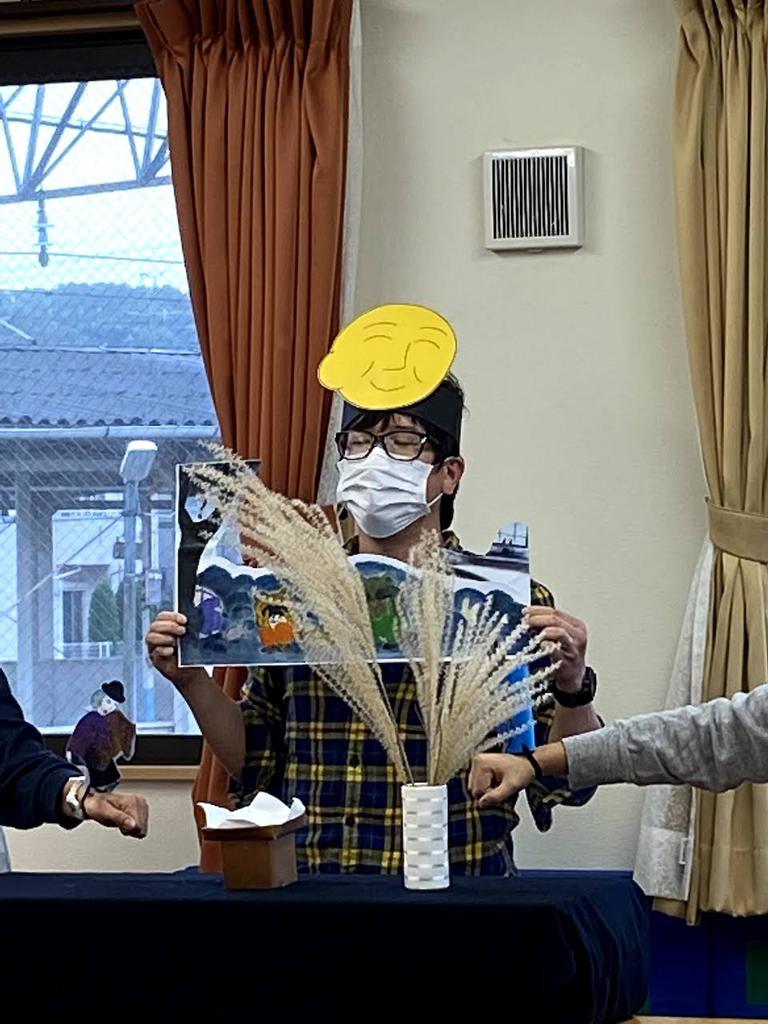


報道されているような「事件」によるものだけではなく、保育の問題の多くは、子どもにとっての環境とは何が必要なのか?という視点で議論がされにくいことではないかと思っています。
率直に現場サイドから必要とする環境づくりと国の基準や要請に乖離があることは、様々なコメンテーターが述べていることですが、そうしたことはもう20年以上前から改善要求として訴え続けてきたことでもあります。
何か大きな「事件」がないと、子どもたちを守りたいという声がかき消され、運営側の自助努力を余儀なくされているところに日本の保育問題の根深さがあると考えています。


保育園にいる子どもたちは様々な月齢、発達差があり、家庭生活の背景が違う子どもが10人、20人といる集団で、ごく普通に行われている活動でさえも、場合によっては、本来の子どもの発達に合わないことを無理にさせれば不適切なことになります。
そうすると、何でも一律に一斉にさせる活動が続くことは、一部の子どもにとってはかなり不適切な保育を日々経験している状態になっている可能性もあります。

では、集団保育の中ではどんな機会を通して子どもの成長発達が保障されていけばいいのでしょう。
その基本的な道筋は、国の保育の指標となる保育所保育指針でも言われている「環境による保育」の内容を掘り下げ、保育園、保育者が学び、実践の中で豊かにしていくことだと思います。
保育園や幼稚園、子ども園に子どもが遊ぶ環境(学ぶ環境)が、いかに提供されているかが「子どもの発達をどう考えているのか」というレベルを表しているでしょう。
具体的には、一日の日課をどう考えるかということからです。
保育園の一日の時間は、保育者にとっても子どもにとっても有限ですし、その中に「子どもに育てたい、心情、意欲、態度」という、年齢や発達に対する指導が教育的な要素として大事にされているなら、
「外で自由に動いて遊べる時間、室内で遊べる時間の長さ」「細切れではなく一続きになっている時間の長さ」がどのくらい子どもに保障されているのか?ということも非常に大事になってくるのだと思います。
子ども自身が「あてがわれた遊び」ではなく、主体的に遊びたいことを見つけて、友達と遊びこめるような時間がなければ、子どもからしたら遊んだことにはならないのですから。
そして、屋外でも室内でも、子どもたちが自由に使える、手に取れる遊具はどのくらいあるのか?も、とても大切な環境条件です。自分たちで自由に選択できず、量もない遊具の環境では、子どもがしたいことを見いだせないとうことになるでしょう。



さらに、ここは配置基準からして現場としては悩ましく、実現されていることが少ないのですが、子ども側の必要な時間帯に、必要な場所に大人がいるか?
つまり、子どもの状況や状態に合わせて援助ができる人的条件がつくれているかということです。
食事や排せつなど、個人差が大きいところは大人の援助が自然にある状態が子どもには必要です。
活動や生活の様々な場面で、子どもがあっちからも、こっちからも「せんせー、やって」「せんせー、できない」と少ない大人を求めて大声で助けを呼び、保育者がそれに「待ってね」「今いけないから」「○○ちゃんが終わってからね」とたくさん待たされることで子どもが「自分でする」意欲をそもそも削いでしまうことにもなっていきます。
そうしたことが極力おこらないように、日々の保育に工夫がされ、多くの園の保育士が責任を果たしたいと精一杯取り組んでいるのですが、当園も含めて圧倒的に必要数の保育者がいない状況は、各園の誠意だけでは解決できない問題でもあり、国や行政を含めた解決策を急いで持たなければと他園と共に行政に働きかけながら、早期の改革を熱望しています。



現実の問題は山積みですが、私たちに今できることは、子どもたちが「したいことがたくさんある」「したいことがじっくりできる」、真に子ども主体の保育を実現することへの努力をし続けること、そしてその環境がより良く創れるよう、可能性を模索し続けていくことだと思います。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。
2023年1月1日
園長 日下部樹江















